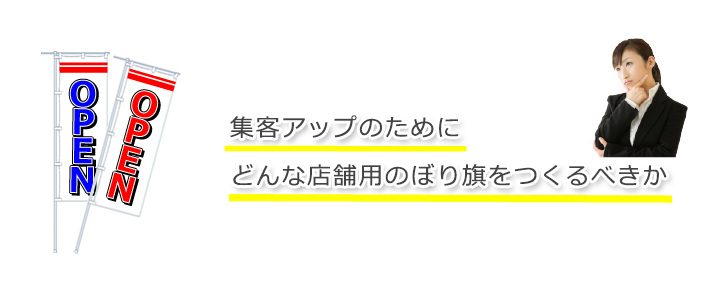
居酒屋のピンチを救う店舗(店舗用)のぼり旗の出番は
価格競争で居酒屋は苦戦が強いられている。これまでの旧態依然とした中途半端な居酒屋はどんどん自然淘汰されて、手軽に飲み食いできる腰掛け感覚の居酒屋が増えたせいだ。それまでの居酒屋は1人あたり2300円~3000円が相場。ちょい呑みといわれるのは1000円台でも呑んで帰れる。
ファミレスや駅近、酒屋の立ち飲み店を改造した店のスタイルで、グループ利用よりもお一人様需要・お二人様需要に軸足を置いている。小さな坪数で展開できるため、急激に店舗数を伸ばした。また店内に大型の生け簀を置いた、産直の漁師系居酒屋も増え、客足はそちらに取られた形だ。
東北各県の地元の漁師が居酒屋を都内に開き、漁港から魚を直接運んでくる。その様子は網を引く段階から店内のVTRで放送されたりして、ダイナミックさが通常の居酒屋とは格段に違う。居酒屋もただ黙っていたのでは生き残れない。経営母体は同じで居酒屋店をブランド扱いした多種多店舗展開も行き詰まっている。
● 客足は、単なる鮮度や安さだけでは捕捉できなくなってきた。
● 気づかいのいらない1人呑み需要に応える場所ができて影響は大きい。
● 客単価3000円前後をキープしないと居酒屋経営は苦しい。
● 周辺には同じ業態のライバル店が多く、小さなパイの食い合いだ。
● スマホ、SNSで新業態に話題集中。コツコツ積上げた努力が皆無になることも。
● 居酒屋は鮮度にも価格にもサービスにも限界がある。従業員は増やせない。
これまで売上の低下に苦しむ店は店内の一部改装や店舗(店舗用)のぼり旗の刷新なども試みてきたが、そのようなことで事態の回復をはかれるような状況ではないという店がほとんど。根本的な取り組みが必要だとも言う。
店舗(店舗用)のぼり旗をサイン代わりに使い活性化
旧来型の居酒屋の泣き所はたくさんあるが、たとえば最近ではスマホの決済システムを導入してレジ係の人員を削減したり、同じくタブレットを使ったオーダーシステムで、外国からの留学生でも対応可能な環境ができあがったりしている。また次のような取り組みで業績を伸ばしている居酒屋もある。
●稼動していない居酒屋の昼の時間を女子会に解放した。
●子連れでもOKのママ友サークルに使ってもらっている。
●シニアデー、ファミリーデー、女子会デー、居酒屋研修所にも使っている。
上記の例は一時期経営危機に陥って、その後V字回復を果たした居酒屋業態のA社。最初は昼の時間を女子会に解放しただけだったが、口コミで広がり、ママ友、オタク女子・男子、シニア茶話会などと広げ、いまではスマホ撮影会のスタジオになったり、居酒屋研修の道場になったりもしている。
ユニークなのは店舗(店舗用)のぼり旗の活用法で、たとえば女子会の日ののぼり旗のカラーはピンク。ママ友の日のオレンジ、シニアの日は緑など、色分けして店頭に出している。居酒屋新人研修の日は青色で、この日に限って出し物が無料にもなっている。いまではこうしたのぼり旗の色が暗黙のサインにもなって、新規のシニアが飛び入り参加したり、ママ友が新人を連れてきたりしている。
店舗(店舗用)といえば、のぼり旗は決まってど派手だが、上記の場合は色によるサイン代わりとイベント開催デー・参加特典の告知にそれを使っている。訪れた客は入り口の専用端末にスマホをかざせば、黙っていても特典が受けられるようになっている。決して居酒屋本業の成功例ではないが今後を占う意味では有効だ。
- 店舗用のぼり旗をつくって集客アップを!
- 店舗用のぼり旗には明確な特徴がある!
- 集客アップを実現する店舗用ののぼり旗の特徴
- 店舗用のぼり旗のデザインを決定する
- 店舗用ののぼり旗も意外とおもしろい!
- 一体どうすればいいの?店舗(店舗用)のぼり旗の考え方&捉え方
- 店舗(店舗用)のぼり旗のこれから。ホントに必要なの?効果はあるの?
- 店舗(店舗用)のぼり旗でオーダーメイド。本気で差別化するとしたら?
- キッカケ作りの七つ道具。交流の場に店舗(店舗用)のぼり旗
- お忍びふうでもステキな感じ。店舗(店舗用)のぼり旗
- カッコ良く光る手作り。これからの店舗(店舗用)のぼり旗
- 店舗(店舗用)のぼり旗を、外国人に理解させるために?
- 店舗(店舗用)のぼり旗 ダイニングバーのイメージ戦略とは
- 居酒屋も価格競争。店舗(店舗用)のぼり旗はどこまで役立つ?
- 店舗にのぼり旗を設置する時の注意点や必要な手続き
- あなたの店舗ののぼり旗がグッと効果的になるコツ
- 無地のぼり旗に手書きでデザインして他店舗との差別化を